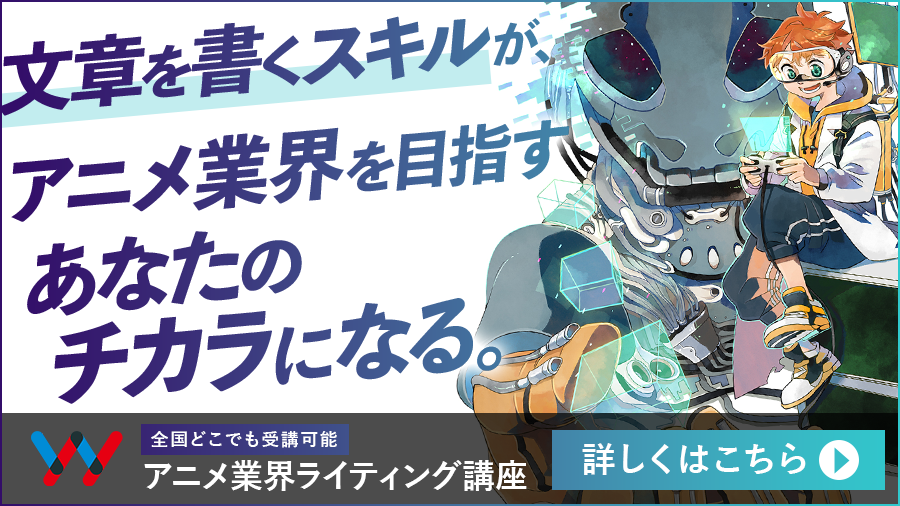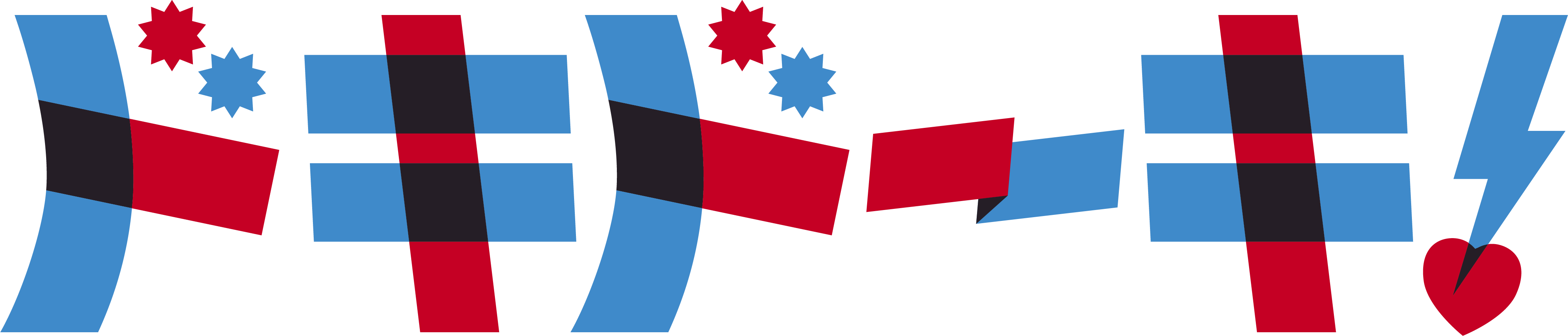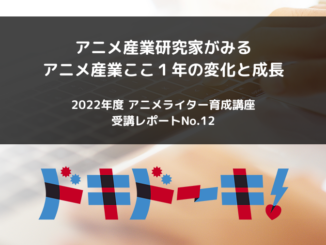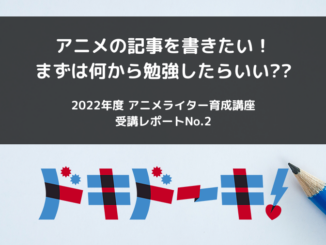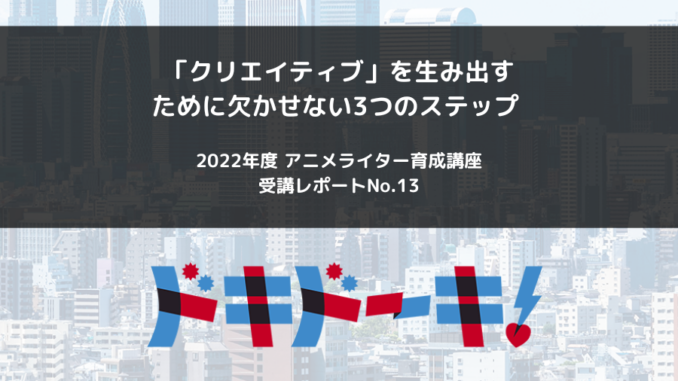
2023年2月25日に、2022年度アニメライター講座の講義がオンラインで行われました。今回はその模様を一部抜粋にてご紹介いたします。
執筆・編集:ドキドーキ!編集部
本日の講師は、物語評論家 さやわかさんです。
今回は、アニメや漫画といったクリエイティブな作品に限らず、評論・批評を書くときなど様々なモノを作るときに忘れてはいけない要素について教えていただきました。
よく「見る人に想像の余地を残してみました…」というコメントをみかけることがありますが、さやわかさんによるとこれは作り手の甘えだそうです。
作品は相手に伝えることが前提であるため、作り手の考えていることが確実に受け手に伝わる必要があるのです。
では、受け手のことを考えて作品をつくるにはどうすればよいのでしょうか?
ここでは、作品づくりで飛ばしてはいけない重要な3つのステップを講義から抜粋して簡単にお伝えします。
①受け手を考える
まずは、「受け手は誰なのか」「どこで発表するのか」を考えることが大切です。
発表するのは、アニメ雑誌の記事なのか、一般新聞のウェブ媒体なのか、週刊少年ジャンプなのか。
受け手は、テレビで「笑点」を見ている人なのか、全国の幼稚園の園児なのか、自分のお母さんなのか、コンビニの店員なのか。
これらの設定は具体的であればあるほど良いです。
例えば、「10~20代の女性」の受け手を想像した場合、その中には小学生から社会人までが含まれることになり、ターゲットは広くなりすぎてしまします。そのため、可能な限り解像度を高める必要があるのです。受け手が明確に見えていればいるほど、ストーリー性が作りやすくなります。
②受け手の反応を考える
次に、受け手として設定した人たちに「どんな感情を抱かせたいか」を考えます。
「かっこい・かわいいと思ってほしい」といった淡白な感情ではなく、「どういう風にかっこいい・かわいいのか」のように具体性を持たせましょう。
③その感情を抱かせるためのストーリーを具現化させる
起こしたい反応とストーリーが決まったら、具体的に「〇〇のキャラクターが〇〇する」というようなストーリーをつくります。
クリエイティブの現場では一番最後の「ストーリー」から考えられることもありますが、まずは誰に何を伝えるかという点を明確にする必要があるのです。この順番は必ず守られるべきでしょう。
マンガの原作から評論まで幅広く作品を世に届けているさやわかさん。
作品の種類に関わらず共通するモノづくりの順番について知るとても良い機会となりました。
~~~
2023年度の「アニメ業界ライティング講座」は現在受講申込受付中です。ご関心のある方は是非こちらから詳細をご確認ください!