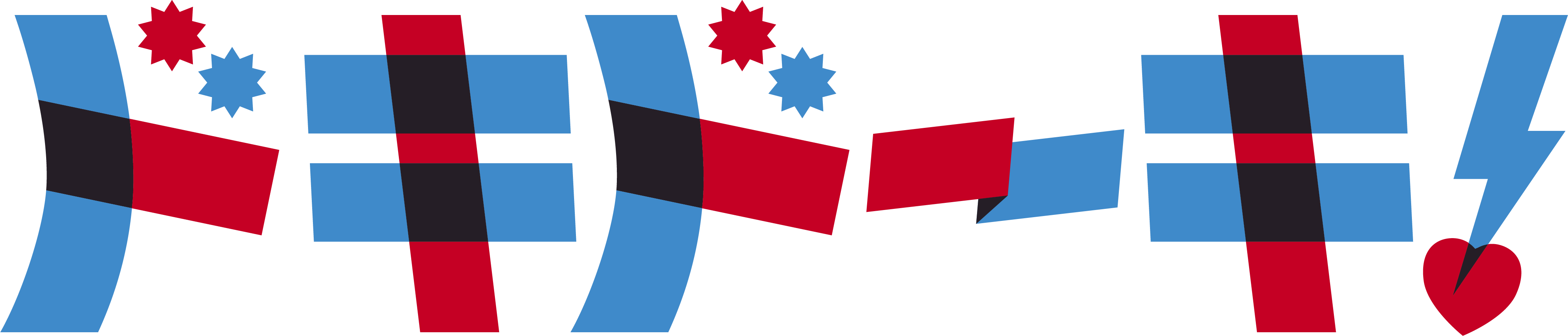2025年3月24日~3月25日にAnimeJapan 2025 ビジネスデイが開催された。本記事では、会期中に開催されたセミナー『世界を魅了する日本のアニメ トムス・エンタテインメント / MAPPA / Netflixの挑戦』をもとに、Netflixが仕掛けるアニメ戦略について紹介する。
執筆:はらぐち かずや
編集:ドキドーキ!編集部
本セミナーには株式会社MAPPA 大塚学氏(代表取締役社長)、株式会社トムス・エンタテインメント 吉川広太郎氏(取締役 上席執行役員 兼 営業本部長)、Netflix 坂本和隆氏(コンテンツ部門 バイス・プレジデント)、そして司会として徳力基彦氏(noteプロデューサー/ブロガー)が登壇した。
海外でアニメは観られているのか?
坂本氏によれば、2025年現在、Netflixには世界で3億世帯以上が加入しており、約7億人が利用している。アニメの視聴者は年々増加しており、過去5年でNetflixメンバーのアニメの視聴時間は約3倍に増加した。全世界のNetflixメンバーの約50%がアニメを視聴したことがあるという。また、日本語コンテンツは、英語、韓国語に次いで視聴されている。
吉川氏は、アニメの世界的な認知度向上を実感した事例として、Netflixで独占配信された『範馬刃牙』が世界ランキングのトップ10入りを果たしたことを挙げる。
吉川氏「『バキ』のアニメ化企画が決まった際、Netflixに独占配信を提案した。当時、原作である秋田書店のコミックは、一部のアジアの国・地域を除き、正規品として海外に流通していなかった。そのため、『バキ』の世界的な認知度は決して高くなかった。」
世界的な認知が見込めない中で、Netflixはなぜ『バキ』の全世界独占配信に踏み切ったのだろうか。
坂本氏「現在、Netflixではローカルforローカルの戦略を重要視している。グローバル展開を急ぐのではなく、各国のローカルチームがそれぞれの地域性を意識した作品を制作、調達し、配信している。『バキ』には物語・キャラクター性の強さがあり、今も連載が続いている長寿作品である。トムス・エンタテインメントが用意した映像資料を視聴し、具体的な配信のゴールが見えてきたため、契約が進んだ。」
また大塚氏は、2016年から2018年の間に公開したオリジナル作品が海外で評価を得たことで、新たな道が開けたという。
大塚氏「オリジナル作品は、日本国内でもどのような反応が出るか未知数だったが、海外のお客様が熱狂的に支持してくださった。そして、海外市場を分析する中で、ジャンプ原作の存在感が強いと感じた。この経験が、『呪術廻戦』の制作につながっていく。」
海外でもアニメが見られるようになった背景には、視聴環境の変化があると坂本氏は指摘する。
坂本氏「インターネット環境さえあればどこでも作品を見られるだけでなく、字幕・吹き替えの充実も大きい。現在は字幕で34言語、吹替で8~12言語をカバーしている。吹替では、声優のキャスティングも重要視している。ストレスのない視聴環境と、作品ラインナップの幅広さが、海外でのアニメ視聴を後押ししている。」
さらに、アニメは実写に比べて、全世界の視聴者の期待値が高い傾向にあるという。
坂本氏「アメリカ初のアニメーションと日本のアニメは大きく異なる。日本のアニメは、漫画が大きくヒットし、それがアニメとして映像化されるケースが多い。世界中の視聴者にどのようにアニメを届けていくのか、我々は少しずつ学んでいる。」
なぜ独占配信にするのか?
Netflixが作品を独占配信することで、アニメの権利者にとってどのようなメリットがあるのだろうか。
坂本氏「作品を独占配信にするか、他の配信サービスにも提供するかは、作品ごとにアプローチを変えている。『バキ』シリーズは、全世界でNetflixが独占配信しているが、『SAKAMOTO DAYS』は日本国内では他の配信サービスにも提供されており、1週間先行でNetflix上で見れるようになっている。(『SAKAMOTO DAYS』は国外では独占配信)
Netflixで独占配信すれば、必ずしもその作品が多くの視聴者に観られるというわけではない。しかし、独占配信にすることで、Netflix社内チームの作品に対する理解度・コミットメントが大きく向上する。Netflixは190か国以上に作品を配信しているが、各地域で宗教・文化・習慣は全く異なる。作品の文脈を捉え、各国でどのようにプロモーションを展開するかが重要となる(ソーシャルメディア展開など)。社内での作品に対する理解度やコミットメントが深まれば、それをプロモーションに活かすことができる。
日本・海外で独占配信した方が作品が活きることもあれば、逆にマイナスになることもある。その点を念頭に置いたうえで、どのスキームがベストかを権利者・スタジオと丁寧に話し合っている。」
大塚氏「『らんま1/2』は、国外でNetflixが独占配信しているが、地上波では日本テレビでも放送している。日本国内ではアニメをテレビで見る習慣があるため、地上波でも放送した方がNetflixでも観られるようになると考えた。」
製作委員会の組成はどのように変わったか?
近年、アニメの制作費を調達する方法が大きく変わりつつある。例えば、『チェンソーマン』はMAPPAが制作費を100%出資したことで大きな話題を呼んだ。
大塚氏「チェンソーマンの制作費用を100%出資したという話がひとり歩きしているが、1社で作品を製作することが目的ではない。歴史のある大きな会社では、100%出資をやろうと思えばできる。MAPPAが100%出資で作品を制作した先に、お客さんや取引先にどのようなメリットがあるのかを感じてもらいたい。課題はまだあると感じている。」
また、吉川氏によると、製作委員会の組成も変化しているという。
吉川氏「昔は製作委員会に6社~8社など、多くの会社が入っていた。最近は委員会メンバーの数を少なくし、2社~3社で座組を組むことがある。」
大塚氏「製作委員会に入っている会社が多くて出資比率が低いと、ヒットした時に入ってくるお金も少なくなる。近年はリスクとヒットした時のリターンのバランスが良い形で製作委員会を組成できるようになってきた。」
アニメを独占配信にすると、配信サービス事業者から製作委員会に対して多額のライセンス料が支払われ、制作費を調達しやすくなることがある。制作費が大きければ、余裕をもって宣伝や制作を行うことができる。
坂本氏「多面的にメディアでプロモーションを行おうとすると、限られた予算では十分に宣伝を行えないことがある。制作プロダクションと直接アニメをつくることで、日本をはじめ全世界でプロモーションを仕掛けることができる。同時に、制作プロダクションのキャッシュフローに余裕を持たせ、制作環境を整えるサポートをしていくことも、Netflixが担う重要な役割だと考えている。」
Netflixは視聴データをどのように活かしているのか
近年、配信サービスのデータをアニメの制作サイドに還元することで、次の作品づくりに役立てているケースがある。Netflixは自身が得ているデータを、どのように作品制作に活かしているのだろうか。
坂本氏「そもそもNetflixは、年齢やジェンダーなどの個人情報をサービス上で使用していないため、パートナーからよくリクエストを受ける、国籍や年齢層などの詳細データは提供していないが、クリエイティブの内容面でのフィードバックを共有することはある。
例えば、アニメのどの話数で離脱した人がいるかなどを分析し、脚本の打ち合わせの中で予想される視聴者の反応を制作サイドと会話している。コンテンツの精度を上げるために、Netflixのデータを生かして、物語のリズムやキャラクターの魅力を活かす方法を制作サイドと話し合うことが多い。」
昨今は配信サービスの普及や視聴環境の変化により、世界中の視聴者が日本のアニメに触れる機会が増えている。今後も制作サイドと配信プラットフォームの連携により、さらなるヒット作品が生まれることだろう。