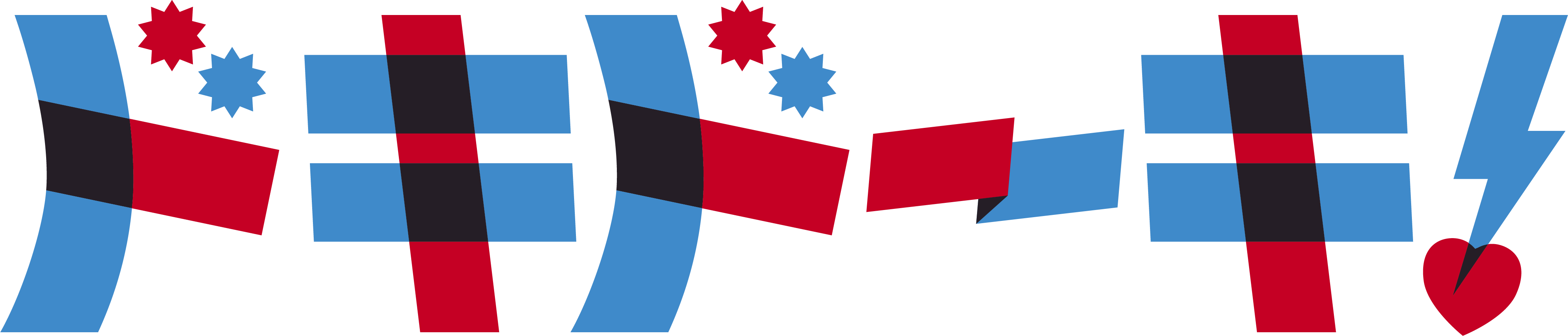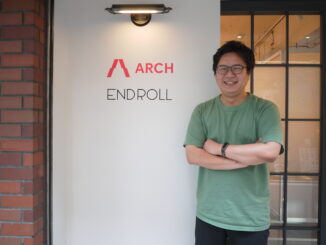1997年に創立の総合エンターテイメント会社、株式会社マーベラス(https://corp.marv.jp/)。そこでプロデューサー・MD(マーチャンダイジング)担当として2.5次元舞台に携わる湯田瑞穂(ゆだ・みずほ)さんに、舞台制作というお仕事の内容を伺いました。湯田さんの学生時代から入社にいたるまでのお話から、舞台制作という仕事の醍醐味、そして就活生に向けたアドバイスまで、たっぷりとお話しいただきました。
2.5次元舞台の世界で働きたい方はもちろん、アニメやゲーム作品の演劇・舞台の仕事に興味がある方にとっても必読の内容です。ぜひとも、ご覧ください。
取材:いしじまえいわ
文:遠藤聡平
編集:中山英樹
2.5次元舞台とはどういった世界なのか
――まず最初に、マーベラスがどのような会社で、湯田さんがどういった事業に関わられているのか教えてください。
湯田瑞穂さん(以下、湯田):マーベラスは総合エンタメ企業で、社員数としては、全体で700名ほどが在籍しています。
事業は大きく3分野、デジタルコンテンツ事業(コンシューマゲーム・オンラインゲーム)とアミューズメント事業(アミューズメントゲーム)、そして音楽映像事業(アニメ・舞台など)を展開しています。ゲームでは『牧場物語』シリーズや、ゲームセンターでプレイできる『ポケモンフレンダ』などのタイトルに耳馴染みのある方も多いかもしれません。
私が所属しているのは、音楽映像事業のうちのライブエンターテイメント事業部。マンガやアニメ、ゲームなどを原作とした舞台・ミュージカル作品(以下、2.5次元舞台作品)の企画・制作・興行を行う部署です。
――具体的にはどういったお仕事をされているのでしょうか。
湯田:制作プロデューサーやMD担当として、年2~3作品の舞台制作、グッズの企画開発から製造・販売管理などの業務を担当しています。
直近では2024年11月に上演した舞台『アオペラ』という作品にプロデューサーとして携わりました。今は『Dancing☆Starプリキュア』The Stage2のMD担当として公演グッズの制作を行いながら、2025年~2026年上演予定の舞台の準備をしています。プロデューサーの仕事は、出版社などの版権元からの舞台化許諾、製作委員会の組成、予算・スケジュールの管理、スタッフィング・キャスティング、打ち合わせや稽古への立ち合い、SNSの運用、さらに公演のBlu-ray/DVDのチェックも行います。2.5次元舞台は原作のある舞台なので、脚本から劇中に投影する映像や小道具ひとつに至るまで、版権元に監修いただくのも大事な仕事です。
――企画の立ち上げから公演が終わったあとまで多岐にわたる仕事なんですね。舞台作品の企画立ち上げは、例えば原作となる漫画を読んで、この作品を舞台化したいと考えたりすることから始まるのでしょうか?
湯田:誰かが「この作品を舞台で観たい!」「この作品は舞台化に向いている!」と思うことから、舞台の企画がスタートすることが多いです。どうしたら原作の魅力を舞台ならではの表現できるか企画書を練ります。
――MDの仕事についても教えてください。
湯田:全体を通して予算とスケジュールの管理をする点はプロデューサーと同じですね。作りたい商品についてメーカーと価格や仕様について交渉、撮影のディレクション、デザイナーとデザインについて相談、チケットの販売状況などを加味して製造数を決めるのも仕事です。その中で、パンフレットにどういった内容を盛り込んだらより読みたいと思ってもらえるか、作品らしさを表現できるペンライトの形は?など作品性を出していく面白さがあります。
――舞台作品や公演グッズの企画について、いろいろと考えることは多いと思うのですが、湯田さんはどのようなことを考えながらお仕事をされているのでしょうか。
湯田:原作として面白いことと舞台化して面白いことが必ずしもイコールではないので、舞台化することで、いかに作品の魅力を新しい角度から表現できるか、ということを常に考えています。
作品のどういうポイントを「面白い!」と思っていて、それを舞台で表現するには歌があったほうがいいのか、ないほうがいいのか、どんな演出家のテイストが合うか、など……。
ターゲットとする客層もかなり意識しています。客層によって、喜ばれるグッズの種類やテイストも異なるので、学生のキャラクターがメインなら学校生活を切り取ったようなグッズが喜ばれるかな、とか考えたり。
「ガクチカ」は必ずしも舞台に関わることでなくてもよい!?
――話は変わりますが、湯田さんの入社の経緯をお聞かせください。もともと舞台がお好きだったのですか?
湯田:東北で育ったのですが、物心ついた頃から「子ども劇場」と呼ばれる月会費を払って年に数回お芝居を見る集まりに参加していたので、舞台はずっと身近なものとして過ごしてきました。舞台の仕事に興味をもったのは小学校高学年の頃。「音楽座ミュージカル」というミュージカル劇団の「アイ・ラブ・坊っちゃん」という作品を観劇したのがきっかけです。あまりの面白さに心を鷲掴みにされ、それから大学受験が本格的になるまでは公演があれば家族で観劇に出かけていました。当時、将来の夢はミュージカルの俳優になることでしたが、現実を見過ぎる性格のため、幼少期からダンスを習っていない自分が俳優になれるわけない、と早々に諦めました(笑)。
――漫画やアニメには触れていたのですが?
それが、当時親が見せてくれなくて…… 。
中学2年の春休み、母親の実家に1週間程滞在する機会があって、親の目の届かないところで、ケーブルテレビで放送されていたアニメ『銀魂』を見たのが、ほぼ初めてのアニメ体験です。「世の中にこんなに面白い作品があるのか!」と夢中になりました。それから大学受験までの間は、授業中に板書をノートにとる際、全部『銀魂』のキャラクターの口調で書き、銀さん(坂田銀時)たちに勉強の解説をしてもらって……、と勉強のモチベーションを維持するという生活をしていました(笑)。
――大学で学んだこと、および大学生活での活動の中で、今のお仕事につながっているなと思うことがあれば、教えて下さい。
湯田:そんなこんなで、「サブカル」って格好良いと思って、大学では何でもやらせてもらえそうな社会学を専攻しました。友人も自然とアニメやマンガといったコンテンツが好きな人が多くなりました。今の仕事に大きく影響していることといったら、大学の先輩に誘われてコミケスタッフをはじめたことですかね。参加者対応やサークル出展スペースの安全管理を担当していて、そこでコミックマーケットという場に集う人達のサポートをする経験をしたことが、「スタッフとして携わるイベントって楽しい!」と思う原体験になりました。意外と仕事に役立ったのは、広く混雑した会場内で「走らないでください!」「一斉点検にご協力ください!」と大きな声を出していた経験で、舞台の現場でも声が通ることでコミュニケーションが円滑に進んだ経験は多いです。
それと結果論ですが、就職活動でもコミケスタッフの経験はウケがよかったですね(笑)。
―であれば就職活動もすんなり方向性が決まりそうですね。
湯田:最初はエンタメ業界に絞って就職活動をしていたわけではないんです。ただ他の業界も説明会や選考に参加してみたものの、自分がそこで働いている姿を想像できなくて、かといって「好き」を仕事にすることが自分に向いているのかの自信も持てずに悩んでいました。
そんな中、友人に誘われてミュージカル『テニスの王子様』を観に行きました。そこで、キャストの芝居、衣裳ヘアメイクや音響や照明といったスタッフワークに、劇場で観劇されているお客様が加わってはじめて完成するという、舞台の「今、この瞬間」にしか見ることのできない緊張感やドラマ性に心が震えて。そして、自分よりも年下の方や、初舞台の方も出演していたのですが、彼らが公演期間や作品シリーズを通して、役者として成長していく、こういう成長を追えるのは2.5次元舞台というジャンルの大きな特徴の一つだと気付いたんです。「2.5次元舞台って面白い!やっぱり人の心を動かす『舞台』を作る仕事がしたい!」とマーベラスに応募することにしました。原点回帰ですね。
入社後のキャリアパスと仕事の醍醐味
――入社して最初にやった仕事は?
湯田:私の場合、2週間程全社の新卒研修があって、4月半ばからはOJTとして6月の舞台公演準備に参加することになりました。最初に担当したのは、劇場でのロビー業務です。当日券など劇場で販売するチケットを管理したり、特典物の配布窓口に立ったり、トラブル対応をしたり、お客様に一番近いところで様々な業務を経験しました。あとは、先輩社員につきっきりで、舞台制作とは、プロデューサーとはどんな仕事なのかを見て学びます。私が最初に参加したのは「『家庭教師ヒットマンREBORN!』the STAGE」(以下、『REBORN!』)の2作目でした。各種打ち合わせへの参加や資料作成はもちろん、公演前に1カ月程度行う稽古にも毎日通い、舞台が形になっていくさまや、そこにどうかかわるのかを少しずつ理解しました。SNSに投稿する画像を作成したり、文章を考えるといったプロモーションにも携わったのですが、お客様の反応がダイレクトにわかるのでやりがいを感じましたね。
――入社から5年半が経った現在の湯田さんの働き方についても教えてください。
湯田:現在は主にプロデューサーとして、2~3本の作品を並行して動かしています。私の職種は裁量労働制なので、この時期までにこれを全部終えないといけないな、じゃあ今週はここまで進めよう、と自分自身でスケジュールを決めて働いています。会社にいて資料作成などデスクワークや会議を行う日もあれば、オーディションやスチール撮影に立ち会うために丸一日外出していることも。
――一番いそがしいタイミングは?
湯田:稽古に入ってから公演が終わるまでの期間ですね。稽古は午後帯から夜までが基本で、毎日立ち合っています。稽古場では、予定通り稽古が進んでいるかを確認するのはもちろん、劇中で登場する衣裳や小道具など、稽古が進む中で決まっていく事項もたくさんあるので、新たに版元に確認すべき事項はあるか、予算を超過しそうな事項はないか……様々な事に目を配っています。
稽古が休みの日は出社して事務仕事を片付けたり、別の作品の打ち合わせに参加したり、ゆっくり休める日はなかなかないですね。
――以前、別のインタビューでは「終わりのない文化祭をずっとやってる」と言っていた人もいました。
湯田:まさにその通りです(笑)。ただ文化祭と大きく違うのは、私達は複数の作品に同時に関わるという点でしょうか。次から次へと違う作品の仕事と締切が迫ってくるので、本当に文化祭が終わることはありません(笑)。
コロナ禍が残した爪痕はいまだ完全に癒えてはいない
――その後2020年頃からは新型コロナウイルス感染症が全国で蔓延し、多くの舞台が中止になっていました。
湯田:当時はアシスタントプロデューサーとして働いていて、なんとかして公演を上演するため、稽古がはじまる前に関係者全員でPCR検査を受けたり、舞台上で役者にマウスガードをつけてもらったり、業界全体的に手探りで努力をしていました。それでも私自身、担当していた公演が中止になって悔しい思いをした経験もあります。スタッフ・キャスト全員で公演を上演する、ということが当たり前でないと痛感しましたね。
――2024年以降、舞台業界もコロナ禍以前の状況の活況が戻ってきている感じがするのですが、コロナ禍以降で大きく変わったことはありますか。
湯田:一番大きな変化はチケットの金額だと思います。また、人件費や各種資材の高騰が続いています。結果的にチケット代を上げざるを得ず、最近はチケット価格が1万円を超えることも多く、お客様に対して心苦しい状況です。
だからこそ、「原作の“舞台化”」として楽しんでいただけることはもちろん、一つの舞台公演として満足していただけるような作品にしなければならない、ということを一層感じるようになりました。
――業界全体としても転換点を迎えているんですね。今後の湯田さんの目標を教えていただけますか。
湯田:観てくださった方が「明日からも頑張ろう」と思えるような作品を作り続けたいです。
2.5次元舞台作品の面白いところって、必ず「その公演が人生初舞台観劇」という方や、原作となる作品に初めて触れる方がいらっしゃることで。その観劇体験をきっかけに、「舞台って面白い!」と他の舞台にも興味を持っていただいたり、原作だったり、他の舞台だったり、役者だったり、興味を広げていただけたらこの上なく嬉しいですね。
――貴重なお話ありがとうございました! 最後に、就活生に向けてメッセージをお願いします。
湯田:ぜひ、学生の間に色々なものに触れて、挑戦して欲しいです。
私は学生時代に「舞台をつくる」という経験はしていなくて、「舞台制作」とは何をするのか、「プロデューサー」って何なのか、正直全然わからない、という状態で業界に飛び込みました。
けれど、コミケスタッフの経験や居酒屋での接客バイトなど、やっているときは就職活動や就職後の仕事で役に立つと思ってもいなかった経験が、意外なタイミングで活きてくることがありました。逆に、映画や音楽などにもっと興味の幅を広げておけばよかった、と後悔もしています。
引き出しは多すぎることはありません!ぜひ食わず嫌いせず、「好き」を増やしていってください。
――ありがとうございました!